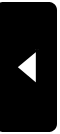2009年03月24日
帰ってきました。
冬に夏物が売ってないのは辛いさね。
ということで1月から熱帯地方の方へ飛ばされていた。電気とガスと水道とネットのある環境は久しぶり。感動してます、かなり。
ヒル山盛り状態の場所だったせいで相当苦しめられて、服が数着血まみれになって洗っても落ちなくなって処分した。ヒル対策でまともなもんちゃんと持って行くべきだった。あと、服やその他が洗っても乾かない超高温多湿地だったが、アークのパリセード、ファイントラックのストームゴージュ、ミズノの薄手のクイックドライのシャツは乾かずとも着ることが出来て好都合だった。KAVU帽子、ノースフェースのタオルマフラー、MSRのパーソナルタオルはいずれも途中で腐臭を放ち始めて少々苦しんだ。とりあえずMSRパーソナルタオルに関しては乾かずとも使えるので、毎日体洗うたびに臭い等がリセットされていたのでまあまあ。手ぬぐいのほうがよいように思った。モントレイルのハードロックミッドは途中で崩壊が始まって帰る頃には水が漏れるようになったので帰国後破棄。軽くて歩きやすかったし、一応最後まで保ってくれたのでそれなりに良かったと思う。そんなもんでしょうか。遊びに行っていたツケがどっさり回ってきていて寝る間もないくらいに忙しいため低調な更新頻度なままであろうことが予想されますが、たまには見に来て下さると嬉しく思います。
というより、全く更新していない期間もそれなりに高いアクセス数を維持していて驚いたのと同時に少々申し訳なさまで感じてしまいます。いつのまにか10万ヒットを越えて久しいようで、これまた何らかの形で皆様にお返しをせねばなりませんね。
個人的な課題はヒル、ダニよけを今後どうやって確実なものにしていくかというのが最大の課題かも。ズボンの裾を靴下に入れると下からのものはそれなりに防げるのだけど上から降ってくる分はやっぱり難しい。
ということで1月から熱帯地方の方へ飛ばされていた。電気とガスと水道とネットのある環境は久しぶり。感動してます、かなり。
ヒル山盛り状態の場所だったせいで相当苦しめられて、服が数着血まみれになって洗っても落ちなくなって処分した。ヒル対策でまともなもんちゃんと持って行くべきだった。あと、服やその他が洗っても乾かない超高温多湿地だったが、アークのパリセード、ファイントラックのストームゴージュ、ミズノの薄手のクイックドライのシャツは乾かずとも着ることが出来て好都合だった。KAVU帽子、ノースフェースのタオルマフラー、MSRのパーソナルタオルはいずれも途中で腐臭を放ち始めて少々苦しんだ。とりあえずMSRパーソナルタオルに関しては乾かずとも使えるので、毎日体洗うたびに臭い等がリセットされていたのでまあまあ。手ぬぐいのほうがよいように思った。モントレイルのハードロックミッドは途中で崩壊が始まって帰る頃には水が漏れるようになったので帰国後破棄。軽くて歩きやすかったし、一応最後まで保ってくれたのでそれなりに良かったと思う。そんなもんでしょうか。遊びに行っていたツケがどっさり回ってきていて寝る間もないくらいに忙しいため低調な更新頻度なままであろうことが予想されますが、たまには見に来て下さると嬉しく思います。
というより、全く更新していない期間もそれなりに高いアクセス数を維持していて驚いたのと同時に少々申し訳なさまで感じてしまいます。いつのまにか10万ヒットを越えて久しいようで、これまた何らかの形で皆様にお返しをせねばなりませんね。
個人的な課題はヒル、ダニよけを今後どうやって確実なものにしていくかというのが最大の課題かも。ズボンの裾を靴下に入れると下からのものはそれなりに防げるのだけど上から降ってくる分はやっぱり難しい。
2008年12月29日
フィールドノート
文具屋で売っている事もあると思うのだけど最近減ってる気がする野帳。耐水バージョンも使った事があるけれどページ数が少ないのとカバーが柔らかいせいでいまいち使いづらく感じて普通のモノに戻ってしまった。豪雨でなければ立てて使うだけで濡れも減らせるし、そうそう字が書けない状態にはならないと思う。大体いつもカメラなり持って行くわけで、それらと同様に扱っている限り耐水性は必須の要素ではないと思う。もちろんダイビング中に使うとかであれば耐水紙と耐水ペンがいるのだけれど、私はまだそんな使い方をしたことはないので普通の野帳ばっかり使っている。
ボールペンは水性インクだと溶けるので基本的にシャーペンで書いている。

一冊だけ買うのもあれだけど、たくさん買い込んでもそこまで消費速度の早いものでもないんだけれど、売っているところが少なめなせいか、意外と人に配ると喜ばれる。山仲間がそれなりにいるならまとめ買いしても余ることはないと思う。ハードカバータイプの耐水バージョンもあったことをリンクを貼る際に知ってしまった(リンク先の下の方にあります)。それほど高いものでもないし一度買ってみたい気もする。
今年の更新はこれで最後となります。皆様良いお年を。
そして来年もまたよろしくお願いします。
ボールペンは水性インクだと溶けるので基本的にシャーペンで書いている。

一冊だけ買うのもあれだけど、たくさん買い込んでもそこまで消費速度の早いものでもないんだけれど、売っているところが少なめなせいか、意外と人に配ると喜ばれる。山仲間がそれなりにいるならまとめ買いしても余ることはないと思う。ハードカバータイプの耐水バージョンもあったことをリンクを貼る際に知ってしまった(リンク先の下の方にあります)。それほど高いものでもないし一度買ってみたい気もする。
今年の更新はこれで最後となります。皆様良いお年を。
そして来年もまたよろしくお願いします。
2008年12月28日
今年のベストアイテムその3

MSR パックタオル パーソナル ボディタオル
言わずもがな。タオルは全部これ一枚。夏はお世話になった。旅行に持って行くにもサイズと機能のバランスがいいのでおすすめ。何回紹介してもし足りないくらいのお気に入り。

PETZL(ペツル) デュオLED14
防水のヘッドライト。ハロゲンは劣悪な条件の時に遠方を照らす能力でLEDより向いている。あまり記事にこそしていないものの実はかなり使いまくっています。夜のお山や海などなどあまり褒められたものじゃないお遊びの時に大活躍。雨が降っていたり水没する可能性があるときにはやっぱり代わりになるライトが存在しないのでしょっちゅう最新型に目移りしつつも未だに使い続けている。私が持っているのは今はあまり見なくなった8LEDものだけど、今ではそれより安く14LEDのものが買えてしまう。LEDが増えても特に困る事はないはず。ちなみに、5LEDモデルは電圧の制御回路が入っていないとかで評判いまいちらしいのだけど、これについては詳しく知らない。

OR(アウトドアリサーチ) バックカントリーオーガナイザー
完全に普段使いの小物入れとなってしまったのだけれど、それも使い勝手が良すぎるのが悪いと思っている。使用頻度の高くないカードやら鍵、名刺ケース、などと散らかりやすい小物が大量に入っている。アウトドア用にもう1つ買うべきかどうか迷っているくらいのもの。特に旅行へ行くときなんかはパスポートや航空券も入れられるので便利極まりない。ポケットに入れておく財布とは別にカバンに入れておく貴重品入れとしての使い勝手はなかなかのもの。
2008年12月27日
今年のベストアイテムその2
アークテリクスのpalisade pants
薄くて軽くて乾きやすい上に撥水で着心地もそこそこよい。何日も旅行する場合でも2枚あれば一枚を着ている間にもう一枚を洗って乾かせるので荷物の軽量化にものすごく寄与してくれた。素材だけで適当な速乾をうたっているものが多い中で、こいつは数少ない本当に速乾なウェアの1つだと思う。ファイントラックのものと並んで数少ない信用できる速乾ウェア。大体はウェストのあたりの生地が厚くなっている部分が乾かないし、そこに気を使っているメーカーは相当少ないんじゃないかと思っている。一枚目で便利さ中毒になって海外通販でもう1つ買ってしまったほどである。つい先日のモントレイルシューズの記事でも写真に写っているのはパリセードパンツである。もう寒くなってきてしばらく使わない時期だけど、来年も使い倒す予定の品。どこかの店で自分に合うサイズが安くなっていたら買っておいてもいいかもしれない。

injinji(インジンジ) パフォーマンス ミニクルー
これは5本指ソックスであればどれでも良かったのだけれど、大きな足でもゆったり履けるサイズが存在していて、かつ機能性もよいということでインジンジをチョイス。基本的にはどれでもよかったのだけれど、日本のメーカーのはやっぱり小さめで私には不満だったので、洋物をプッシュしておきます。
OR zealot jacket

実はケチケチしていてあんまり使っていないのでベストにいれるべきかどうか少し悩んだのだけれど、こいつも入れておく。あまり使っていないと言ってもそれは天気の問題だったりで、荷物の中に入っていたことは多かったし、軽いが故にそういうことができていたことを考えるならやはり使いやすくてよいものということになる。フードがかなり大きめなことも評価が高くて、レインウェアのフードを被ったときの圧迫感がかなり少ない。かなり汚れるとわかっいているときには古いモンベルのレインウェアを使うようにしているのでどっちかと言えば必要かどうかよく分からない時に持って行く用の地位に収まっている。胸のポケットも使いやすくてよい。ただ、暑い時期に着ると汗で裏地がベトベトになり、透湿性が低下しそうで精神衛生的にもあまりよくない。軽いし半分諦めて使っているのだけれど、本当は肌に直接触れない使い方をしたいウェアだと思う。
薄くて軽くて乾きやすい上に撥水で着心地もそこそこよい。何日も旅行する場合でも2枚あれば一枚を着ている間にもう一枚を洗って乾かせるので荷物の軽量化にものすごく寄与してくれた。素材だけで適当な速乾をうたっているものが多い中で、こいつは数少ない本当に速乾なウェアの1つだと思う。ファイントラックのものと並んで数少ない信用できる速乾ウェア。大体はウェストのあたりの生地が厚くなっている部分が乾かないし、そこに気を使っているメーカーは相当少ないんじゃないかと思っている。一枚目で便利さ中毒になって海外通販でもう1つ買ってしまったほどである。つい先日のモントレイルシューズの記事でも写真に写っているのはパリセードパンツである。もう寒くなってきてしばらく使わない時期だけど、来年も使い倒す予定の品。どこかの店で自分に合うサイズが安くなっていたら買っておいてもいいかもしれない。

injinji(インジンジ) パフォーマンス ミニクルー
これは5本指ソックスであればどれでも良かったのだけれど、大きな足でもゆったり履けるサイズが存在していて、かつ機能性もよいということでインジンジをチョイス。基本的にはどれでもよかったのだけれど、日本のメーカーのはやっぱり小さめで私には不満だったので、洋物をプッシュしておきます。
OR zealot jacket

実はケチケチしていてあんまり使っていないのでベストにいれるべきかどうか少し悩んだのだけれど、こいつも入れておく。あまり使っていないと言ってもそれは天気の問題だったりで、荷物の中に入っていたことは多かったし、軽いが故にそういうことができていたことを考えるならやはり使いやすくてよいものということになる。フードがかなり大きめなことも評価が高くて、レインウェアのフードを被ったときの圧迫感がかなり少ない。かなり汚れるとわかっいているときには古いモンベルのレインウェアを使うようにしているのでどっちかと言えば必要かどうかよく分からない時に持って行く用の地位に収まっている。胸のポケットも使いやすくてよい。ただ、暑い時期に着ると汗で裏地がベトベトになり、透湿性が低下しそうで精神衛生的にもあまりよくない。軽いし半分諦めて使っているのだけれど、本当は肌に直接触れない使い方をしたいウェアだと思う。
2008年12月25日
今年のベストアイテムその1
ulgさんの山より道具で毎年おなじみの今年の個人的ヒット道具紹介をやってみようと思います。
ネタがないのでパクってみたのですが、情報として書きなぐっておくだけでも誰かの役に立つ事もあるかもしれません。
まずはクッキングシステム編

EPI(イーピーアイ) REVO−3700
実は今年はいくつか火器を買ってしまった年だったのだけど、火力の強さや調節しやすさ、点火スイッチの耐久性ではこいつが一番だと思う。相当酷使しているにも関わらず今のところ何の不具合もなくやっている。使い続けているとメッシュ部分が焼けまくって硬く、脆くなりそうで心配だったのだが、触らなければ特に問題はなさそう。実際のところ使っているうちに硬く脆くはなるけれど耐久性は十分と判断してよさそう。少なくとも点火装置が直接火にあぶられる部分に埋め込まれているものよりずっと長く使えている。軽量なバーナーの中ではスペックは凡庸な感じにも見えるが、使い勝手まで評価すると傑作だと思う。
メッシュが割れて取れても火が使えなくなることはないはずなのでそういう意味でも突然使えなくなる事も少なそうで信頼性もそれなりかと。お山でメッシュが破損したら山にいる間はごまかしながら使って、帰ってきてから買い替えるのがいいような気がする。とはいえ、まだ一度も壊れていないので何とも言えない。

EPI(イーピーアイ) ATSチタンクッカー TYPE3−M
万能チタンコッヘル(だと個人的に思ってる)。スノピのチタントレックにATS加工してもらったものは日帰りでどこかへ行くときによく持って行くし、これも同じ。基本はお湯沸かす程度の気持ちで持って行けるけど、でも時々は米を炊いたりもするような場合でも十分に対応してくれる。もちろんrevo3700とセットで常々愛用中。

佐治武士 漁師マキリ
私が愛用しているのはこれを買う金があれば4本は買える比較的安いものだけど、それを使っていると、この高い奴の細かいところの作り込みが値段だけの価値があるということを見るだけでちゃんと理解出来る(つもり)になってくる。しっかり料理なりする予定がないときは持って行かないようにしているが、マキリを持っているとやっぱり便利である。しかも、ヘビーデューティー系のマルチツールよりは軽いので重くてストレスになることも少ない。安いものは切れ味は劣るが何にでもラフに使えて、高いものは切れ味が鋭くなってそのぶん荒っぽい使い方すると傷みやすくなるというふうに思っている。とはいえ、高いものでも白紙鋼なので研ぎまくって何にでも使う実用品だと思う。まともな鋼の刃物の切れ味を知らない多くの現代人には驚きの切れ味であることは間違いないので気になったらチャレンジしてみてもいいかもしれない。
ただし、砥石を持っていないなら一緒に砥石も買わなきゃ意味がない。
ネタがないのでパクってみたのですが、情報として書きなぐっておくだけでも誰かの役に立つ事もあるかもしれません。
まずはクッキングシステム編

EPI(イーピーアイ) REVO−3700
実は今年はいくつか火器を買ってしまった年だったのだけど、火力の強さや調節しやすさ、点火スイッチの耐久性ではこいつが一番だと思う。相当酷使しているにも関わらず今のところ何の不具合もなくやっている。使い続けているとメッシュ部分が焼けまくって硬く、脆くなりそうで心配だったのだが、触らなければ特に問題はなさそう。実際のところ使っているうちに硬く脆くはなるけれど耐久性は十分と判断してよさそう。少なくとも点火装置が直接火にあぶられる部分に埋め込まれているものよりずっと長く使えている。軽量なバーナーの中ではスペックは凡庸な感じにも見えるが、使い勝手まで評価すると傑作だと思う。
メッシュが割れて取れても火が使えなくなることはないはずなのでそういう意味でも突然使えなくなる事も少なそうで信頼性もそれなりかと。お山でメッシュが破損したら山にいる間はごまかしながら使って、帰ってきてから買い替えるのがいいような気がする。とはいえ、まだ一度も壊れていないので何とも言えない。

EPI(イーピーアイ) ATSチタンクッカー TYPE3−M
万能チタンコッヘル(だと個人的に思ってる)。スノピのチタントレックにATS加工してもらったものは日帰りでどこかへ行くときによく持って行くし、これも同じ。基本はお湯沸かす程度の気持ちで持って行けるけど、でも時々は米を炊いたりもするような場合でも十分に対応してくれる。もちろんrevo3700とセットで常々愛用中。

佐治武士 漁師マキリ
私が愛用しているのはこれを買う金があれば4本は買える比較的安いものだけど、それを使っていると、この高い奴の細かいところの作り込みが値段だけの価値があるということを見るだけでちゃんと理解出来る(つもり)になってくる。しっかり料理なりする予定がないときは持って行かないようにしているが、マキリを持っているとやっぱり便利である。しかも、ヘビーデューティー系のマルチツールよりは軽いので重くてストレスになることも少ない。安いものは切れ味は劣るが何にでもラフに使えて、高いものは切れ味が鋭くなってそのぶん荒っぽい使い方すると傷みやすくなるというふうに思っている。とはいえ、高いものでも白紙鋼なので研ぎまくって何にでも使う実用品だと思う。まともな鋼の刃物の切れ味を知らない多くの現代人には驚きの切れ味であることは間違いないので気になったらチャレンジしてみてもいいかもしれない。
ただし、砥石を持っていないなら一緒に砥石も買わなきゃ意味がない。
2008年12月19日
GX200 gyorome-8
欲しかったカメラが安くなっていた事もあり、追い打ちをかけられたこともあり、ついつい買ってしまいました。フード&アダプターを一緒に購入したためいまいち安いとは言えない値段になった。後悔はしているが反省はしていない。そのかわり使わないであろうレンズキャップやEVFは購入せず。
さっそくゴソゴソと手元にあったおもちゃを装着。

魚露目8号というドアスコープの親玉みたいなレンズを装着。不思議なルックスのカメラの出来上がり!
相当ケラレがあるのでぐーっとズームして画面いっぱいの円形になるところをみつけてズーム位置をマイセッティングに放り込む。焦点距離によっては周辺がかなりひどく流れるのでやっぱりちゃんとした魚眼レンズのかわりには使えないように思う。条件によって周辺の解像具合はずいぶん変わってくるけれど、たぶんこの写真が一番悪い状態だと思う。

全周魚眼状態だと思いのほか構図の決め方が難しくてなかなかこれといった写真が撮れない。
とりあえずあえてピントをずらして周辺の流れごとよく分からなくしてみたり、(手ぶれは予期せずぶれてしまった)引いたり寄ったりして自分のなかでは一番マシかもしれない1枚。

今度はもう少しズームして、光学最大よりさらにデジタルズームすること1.4倍。スクエアモードだとケラレがなくなる。16:9だとデジタルズームの1.6倍でケラレがなくなり対角魚眼っぽくなる。
とりあえず風景を一枚ぱちり。広大な京都盆地の中を流れる大河、鴨川。強烈な遠近感は癖になるかも。画面の隅はあいかわらずひどいのだけど、それほど目立っていないので個人的には許容範囲。

お猫様に大接近!!もう一枚撮ろうとさらに寄ったら目を開けてしまった。このレンズとGX200の特徴であるやたら深いピントの威力を知るには最適な一枚ではないでしょうか。後ろの川の名前までばっちり読める。

そして、このレンズの本来の使用目的とされている魚眼マクロ撮影をやってみた。レンズの先端が当たるまで接近しないと大きく写らないので意外と難易度高い。後ろに木があることが写真を見ると分かる。これだけマクロ撮影して後ろにあるものがしっかり写り込んでいることはちょっと新鮮。

ちょっとトリミングしてリサイズ

等倍切り出し。ここまで写ってくれるのはかなりすごい。

キノコノコノ元気のコ〜。と夜空

いろいろ苦労してさっくりストロボ撮影。でかい外付けストロボ使ってしまえばそれほど苦労はしないのだろうけど、それじゃ持ち運びに苦労することになるのでなんとか持ち運びやすくコンパクトにまとめてみた。
昔買ったはいいけれどあまり使っていなかったソフトスクリーンをアクセサリーシューに差し込み、カメラ銘板に引っかける部分の穴に魚露目8号のレンズを通してやればできあがり。
装着時はこんな感じ

いや、まあなんというか魚眼撮影はほんと楽しい。一眼用のレンズもあるし、そちらはもっとちゃんとした写真が撮れるのだろうけど、どれも全く安くない。一番安い一眼用魚眼レンズであってもGX200と魚露目8号の合計より高くなるし、いい画質とひきかえにでかく重くなってしまう。レンズそのものがでかくなると今度は接写性能が落ちたりピントが少し狭くなったりとよくない部分もあったりする。やっぱりこういう変なことをするには、フルオートなコンデジだと言う事聞かないことがあったりしていらいらすることもありそうだが、一応マニュアルでいじれるGX200だとそういう心配はほとんどしなくて済んでしまう。最近は安くなってきたし、お手軽に魚眼撮影を楽しんでみたいならかなりおすすめできる組み合わせ。とにかく飽きるまでしっかり楽しむ事にしよう。
 ルミクエスト ソフトスクリーン
ルミクエスト ソフトスクリーン
ディフューザーなのでティッシュペーパーでもトレーシングペーパーでもなんでもいいのだけれど、やっぱりそれなりに丈夫なのと扱いやすさから使いやすくていい。値段がついているのもダテじゃない。光の回り方とかはフィルムケースを改造したほうが魚眼向けになると思うのだけど、試していないので何とも言えない。とりあえず手軽に使えるので持っていても無駄にはなりにくい。GX200のフラッシュはマニュアル調光できるのだけれど、発光をフルにして指でフラッシュを覆ってやるとレッドフィルターになってなかなか危ない雰囲気の写真が撮れる。以前どこかのページでそう読んで実際試してみたら確かに赤くなって楽しかった。エマージェンシーな雰囲気の写真になるとでも言えばいいのかな。
 RICOH GX200
RICOH GX200
 GX100・GX200用フード&アダプターRICOH HA-2
GX100・GX200用フード&アダプターRICOH HA-2
さっそくゴソゴソと手元にあったおもちゃを装着。

魚露目8号というドアスコープの親玉みたいなレンズを装着。不思議なルックスのカメラの出来上がり!
相当ケラレがあるのでぐーっとズームして画面いっぱいの円形になるところをみつけてズーム位置をマイセッティングに放り込む。焦点距離によっては周辺がかなりひどく流れるのでやっぱりちゃんとした魚眼レンズのかわりには使えないように思う。条件によって周辺の解像具合はずいぶん変わってくるけれど、たぶんこの写真が一番悪い状態だと思う。

全周魚眼状態だと思いのほか構図の決め方が難しくてなかなかこれといった写真が撮れない。
とりあえずあえてピントをずらして周辺の流れごとよく分からなくしてみたり、(手ぶれは予期せずぶれてしまった)引いたり寄ったりして自分のなかでは一番マシかもしれない1枚。

今度はもう少しズームして、光学最大よりさらにデジタルズームすること1.4倍。スクエアモードだとケラレがなくなる。16:9だとデジタルズームの1.6倍でケラレがなくなり対角魚眼っぽくなる。
とりあえず風景を一枚ぱちり。広大な京都盆地の中を流れる大河、鴨川。強烈な遠近感は癖になるかも。画面の隅はあいかわらずひどいのだけど、それほど目立っていないので個人的には許容範囲。

お猫様に大接近!!もう一枚撮ろうとさらに寄ったら目を開けてしまった。このレンズとGX200の特徴であるやたら深いピントの威力を知るには最適な一枚ではないでしょうか。後ろの川の名前までばっちり読める。

そして、このレンズの本来の使用目的とされている魚眼マクロ撮影をやってみた。レンズの先端が当たるまで接近しないと大きく写らないので意外と難易度高い。後ろに木があることが写真を見ると分かる。これだけマクロ撮影して後ろにあるものがしっかり写り込んでいることはちょっと新鮮。

ちょっとトリミングしてリサイズ

等倍切り出し。ここまで写ってくれるのはかなりすごい。

キノコノコノ元気のコ〜。と夜空

いろいろ苦労してさっくりストロボ撮影。でかい外付けストロボ使ってしまえばそれほど苦労はしないのだろうけど、それじゃ持ち運びに苦労することになるのでなんとか持ち運びやすくコンパクトにまとめてみた。
昔買ったはいいけれどあまり使っていなかったソフトスクリーンをアクセサリーシューに差し込み、カメラ銘板に引っかける部分の穴に魚露目8号のレンズを通してやればできあがり。
装着時はこんな感じ

いや、まあなんというか魚眼撮影はほんと楽しい。一眼用のレンズもあるし、そちらはもっとちゃんとした写真が撮れるのだろうけど、どれも全く安くない。一番安い一眼用魚眼レンズであってもGX200と魚露目8号の合計より高くなるし、いい画質とひきかえにでかく重くなってしまう。レンズそのものがでかくなると今度は接写性能が落ちたりピントが少し狭くなったりとよくない部分もあったりする。やっぱりこういう変なことをするには、フルオートなコンデジだと言う事聞かないことがあったりしていらいらすることもありそうだが、一応マニュアルでいじれるGX200だとそういう心配はほとんどしなくて済んでしまう。最近は安くなってきたし、お手軽に魚眼撮影を楽しんでみたいならかなりおすすめできる組み合わせ。とにかく飽きるまでしっかり楽しむ事にしよう。
 ルミクエスト ソフトスクリーン
ルミクエスト ソフトスクリーンディフューザーなのでティッシュペーパーでもトレーシングペーパーでもなんでもいいのだけれど、やっぱりそれなりに丈夫なのと扱いやすさから使いやすくていい。値段がついているのもダテじゃない。光の回り方とかはフィルムケースを改造したほうが魚眼向けになると思うのだけど、試していないので何とも言えない。とりあえず手軽に使えるので持っていても無駄にはなりにくい。GX200のフラッシュはマニュアル調光できるのだけれど、発光をフルにして指でフラッシュを覆ってやるとレッドフィルターになってなかなか危ない雰囲気の写真が撮れる。以前どこかのページでそう読んで実際試してみたら確かに赤くなって楽しかった。エマージェンシーな雰囲気の写真になるとでも言えばいいのかな。
 RICOH GX200
RICOH GX200 GX100・GX200用フード&アダプターRICOH HA-2
GX100・GX200用フード&アダプターRICOH HA-2
2008年12月18日
椅子猫
プロフィールの写真を初めて変更。一年間雪道の写真で放置してました。
それからブログにアップする写真のサイズもちょっと変えてみました。
なんだか写真が変になってるのが混ざってる?
例えばこれとか

これとか

どうして正方形?
そのへんの詳しい事は明日の朝に!
もう記事は書いてあるので午前5:30ころ自動更新の予定。
久しぶりに京都の街を歩いてきたとかブログのためだけに時間を使うような事をしたので、更新予告だけで一日引っ張ります。
とはいえ、これも自動更新。
それからブログにアップする写真のサイズもちょっと変えてみました。
なんだか写真が変になってるのが混ざってる?
例えばこれとか

これとか

どうして正方形?
そのへんの詳しい事は明日の朝に!
もう記事は書いてあるので午前5:30ころ自動更新の予定。
久しぶりに京都の街を歩いてきたとかブログのためだけに時間を使うような事をしたので、更新予告だけで一日引っ張ります。
とはいえ、これも自動更新。
2008年12月17日
便利な小道具
酷評する人もかなり多いスイステックのユーティリキー。私は今でも結構気に入っているのでいつもキーホルダーについています。洋服のタグを切ったり、梱包をといたり、ビールの栓を開けたりするときに必ずポケットの中にいてくれるのは案外便利なもんです。ドライバーが必要になることもそうそうないけれど、使用頻度の低い道具ほど探すのに苦労するわけで、さっと出せるもので解決できてしまうのはやっぱり便利なわけです。
使用頻度が高かったのと、かなり荒っぽい使い方が多かったせいでプラスドライバーの先端が欠けてしまった。もともとただのステンレスなのでそれほど強度も期待していなかったし、明らかに自分の使い方が悪いので何とも言えないのだけれど、ちゃんとした用途のある鍵と違って荒い使い方をして壊れても問題ないのも利点といえば利点。テコの原理でこじって開けるときにも使っているので少し曲がってしまっているかもしれない。とにかく私にとってはないよりあったほうがいい道具であることは確か。
ナイフは小さすぎてまっすぐ切るのも難しいだとか、ドライバーの精度が悪いだとか欠点だらけなのは確かだけど、すぐ使えるという利点とひきかえであれば我慢できるように思う。あくまでこれ1つでこなそうとするのではなく、簡単なところまではこの道具を使って、できないところは大人しく専用工具を探すというスタンスで使う道具で、アウトドア向きというより普段の暮らしで役に立つアイテムだと思う。

鍵にそっくりな外見

開くとキーホルダーからも自動的に外せる。ナイスなカラクリ。しかも自称程度ながらマイナスドライバー(大と小)でもある。

プラスドライバー(ちょっと欠けた…)。気をつけて使わないと怪我する危ない栓抜き。慣れれば大丈夫。

肝心のブレード。切れ味はいいけれどやはり小さすぎるので期待は厳禁。
 ここが最安。そして説明文が的を得ている。文句言う人も多いんだろうなという印象がする。
ここが最安。そして説明文が的を得ている。文句言う人も多いんだろうなという印象がする。
 こっちはちょっとおしゃれな箱入り。贈り物であればこちらかな。
こっちはちょっとおしゃれな箱入り。贈り物であればこちらかな。

SWISSTECH(スイステック) マイクロパック
ナチュラムにはライトとセットでギフトボックス入りのちょっと高いものがあった。贈り物であればだんぜんこちらをお勧めしたいところ。ナチュラムなので届くまで時間かかる事も多いし、贈り物に使うのであれば余裕をもってかなり早めに買う必要があるのは欠点。
使用頻度が高かったのと、かなり荒っぽい使い方が多かったせいでプラスドライバーの先端が欠けてしまった。もともとただのステンレスなのでそれほど強度も期待していなかったし、明らかに自分の使い方が悪いので何とも言えないのだけれど、ちゃんとした用途のある鍵と違って荒い使い方をして壊れても問題ないのも利点といえば利点。テコの原理でこじって開けるときにも使っているので少し曲がってしまっているかもしれない。とにかく私にとってはないよりあったほうがいい道具であることは確か。
ナイフは小さすぎてまっすぐ切るのも難しいだとか、ドライバーの精度が悪いだとか欠点だらけなのは確かだけど、すぐ使えるという利点とひきかえであれば我慢できるように思う。あくまでこれ1つでこなそうとするのではなく、簡単なところまではこの道具を使って、できないところは大人しく専用工具を探すというスタンスで使う道具で、アウトドア向きというより普段の暮らしで役に立つアイテムだと思う。

鍵にそっくりな外見

開くとキーホルダーからも自動的に外せる。ナイスなカラクリ。しかも自称程度ながらマイナスドライバー(大と小)でもある。

プラスドライバー(ちょっと欠けた…)。気をつけて使わないと怪我する危ない栓抜き。慣れれば大丈夫。

肝心のブレード。切れ味はいいけれどやはり小さすぎるので期待は厳禁。
 ここが最安。そして説明文が的を得ている。文句言う人も多いんだろうなという印象がする。
ここが最安。そして説明文が的を得ている。文句言う人も多いんだろうなという印象がする。 こっちはちょっとおしゃれな箱入り。贈り物であればこちらかな。
こっちはちょっとおしゃれな箱入り。贈り物であればこちらかな。
SWISSTECH(スイステック) マイクロパック
ナチュラムにはライトとセットでギフトボックス入りのちょっと高いものがあった。贈り物であればだんぜんこちらをお勧めしたいところ。ナチュラムなので届くまで時間かかる事も多いし、贈り物に使うのであれば余裕をもってかなり早めに買う必要があるのは欠点。
2008年12月15日
イルミネーション
とりあえず街が鮮やかなのでそれに対抗して光り物でいってみようかと。
まずはいつの間にか手元にあるこれ。

surefire 6PLはLEDモデルになって発熱も減ったので実はアルミボディーでなくともよかったのだけど、この金属の質感に惑わされてこちらを購入。今となっては樹脂ボディーのほうが軽いし、冬は冷たくないし、で良かったんじゃないかと思っている。見てくれの格好良さ以外は値段と重さでG2Lのほうが勝っていることに買ってから気づいてしまった。私もまたアルミボディーの質感に踊らされた哀れな犠牲者の一人なのさ・・・。

光らせて明るさをブログで表現するのは難しいのだけれど、何度か夜に使ってみた感じではかなり遠くまでしっかり照らせる印象を受けた。ただ、慣れの問題もあるのかもしれないけれど、水たまりなんかの発見しやすさはまだキセノンに劣る気がした。霧の中では確実にキセノンランプのほうが視界がいい。このあたりはやっぱりLEDの白っぽい光の欠点なのかとも思うが、それ以外では明るさも電池の保ちも素晴らしいのでやっぱり優秀だ。
褒めておいて、最後にこういう事言うのもあれなんだけど、surefireのライトはアウトドアにはあんまり向いていないように感じる。明るさを一定に保つカラクリが中に入っているおかげで電池交換のタイミングが少し難しいのがその理由。もちろん、スイッチのこともある。やっぱり一定の光量を常に確保したいとかそういうちょっと特殊な要求がないかぎりあんまりオススメしないかも。だらだら暗くなっていくのは我慢ならんという人にも一応オススメはできるかな。
私は暗所での撮影用照明として利用中。この用途だと性能は実用限界の暗さだけど、なんとかギリギリで使える。もちろん撮影条件の制限はかなり厳しいので、近く発売されるとずっと前から言われているもっと明るいものが気になって仕方ない。

SUREFIRE(シュアファイア) 6PオリジナルLED BK
ちなみに、他の類似品と違うのは明るさの表記が0.6倍になっているらしいことと照射パターンにムラがないこと、そして常に一定の明るさをキープしてくれる事。値段の差はほとんどこれだけが理由といってもいいくらい。いつも決まった性能を発揮してもらわないと困るような用途には最適だと思う。

SUREFIRE(シュアファイア) G2ナイトロンLED ブラック
やっぱりこっちのほうが軽くて安くておすすめ度は高いかも。
ちなみに、職質でもsurefire系だとものによっては逮捕、没収食らう恐れがあるような気がします。男性でディフェンダー系のライトを所持してるとビクトリノックスの最小より攻撃的に見えるのでアウトそうな気がします。そして懐かしのポーキュパインは限りなく黒に近い気がします。アルミボディでも一応金属の棒なので人によってはアウトになりかねないんじゃないでしょうか。樹脂製ならさすがに大丈夫でしょうが、経験者の話によると最初から逮捕ありきの口実探しらしいので場合によってはどうかなって感じです。
まずはいつの間にか手元にあるこれ。

surefire 6PLはLEDモデルになって発熱も減ったので実はアルミボディーでなくともよかったのだけど、この金属の質感に惑わされてこちらを購入。今となっては樹脂ボディーのほうが軽いし、冬は冷たくないし、で良かったんじゃないかと思っている。見てくれの格好良さ以外は値段と重さでG2Lのほうが勝っていることに買ってから気づいてしまった。私もまたアルミボディーの質感に踊らされた哀れな犠牲者の一人なのさ・・・。

光らせて明るさをブログで表現するのは難しいのだけれど、何度か夜に使ってみた感じではかなり遠くまでしっかり照らせる印象を受けた。ただ、慣れの問題もあるのかもしれないけれど、水たまりなんかの発見しやすさはまだキセノンに劣る気がした。霧の中では確実にキセノンランプのほうが視界がいい。このあたりはやっぱりLEDの白っぽい光の欠点なのかとも思うが、それ以外では明るさも電池の保ちも素晴らしいのでやっぱり優秀だ。
褒めておいて、最後にこういう事言うのもあれなんだけど、surefireのライトはアウトドアにはあんまり向いていないように感じる。明るさを一定に保つカラクリが中に入っているおかげで電池交換のタイミングが少し難しいのがその理由。もちろん、スイッチのこともある。やっぱり一定の光量を常に確保したいとかそういうちょっと特殊な要求がないかぎりあんまりオススメしないかも。だらだら暗くなっていくのは我慢ならんという人にも一応オススメはできるかな。
私は暗所での撮影用照明として利用中。この用途だと性能は実用限界の暗さだけど、なんとかギリギリで使える。もちろん撮影条件の制限はかなり厳しいので、近く発売されるとずっと前から言われているもっと明るいものが気になって仕方ない。

SUREFIRE(シュアファイア) 6PオリジナルLED BK
ちなみに、他の類似品と違うのは明るさの表記が0.6倍になっているらしいことと照射パターンにムラがないこと、そして常に一定の明るさをキープしてくれる事。値段の差はほとんどこれだけが理由といってもいいくらい。いつも決まった性能を発揮してもらわないと困るような用途には最適だと思う。

SUREFIRE(シュアファイア) G2ナイトロンLED ブラック
やっぱりこっちのほうが軽くて安くておすすめ度は高いかも。
ちなみに、職質でもsurefire系だとものによっては逮捕、没収食らう恐れがあるような気がします。男性でディフェンダー系のライトを所持してるとビクトリノックスの最小より攻撃的に見えるのでアウトそうな気がします。そして懐かしのポーキュパインは限りなく黒に近い気がします。アルミボディでも一応金属の棒なので人によってはアウトになりかねないんじゃないでしょうか。樹脂製ならさすがに大丈夫でしょうが、経験者の話によると最初から逮捕ありきの口実探しらしいので場合によってはどうかなって感じです。
2008年12月11日
バーゴ デカゴン トライアド
たまにはここを読んでいる層に受けそうなことを書かないとアクセス数の低下が心配になってきました。とか言う割にめんどくさいのでブログランキング貼らなくなってますが、皆様忘れずに時々は見てくれると嬉しいです。
なぜか手元に2種類もあるこのキワモノをまたもや引っ張り出してきました。

VARGO(バーゴ) チタントライアドXEストーブ
久しぶりに値段見たけど、こんなものでこれほど高いものをよく買ったものだと我ながら呆れるお値段。より実用的なものはもっと安いんだし。

VARGO(バーゴ) デカゴンチタンストーブ
これもナチュで売っていた。昔は結構レアアイテムだったのに、普及したのね。まあ、こいつは一体型だしちょっと踏んでもたぶん壊れないし、小さめの鍋もなんとか使えるので買うならこっちでしょうね。買ったときは継ぎ目に穴が空いていてアルコール漏れまくりだったので耐火パテで穴を塞いだのはいい思い出。その後穴から漏れることはないのでおおむね満足。穴開き率は結構高いので通販でハズレを引いたら自分で修理したほうが交換より確実かも。トライアドも最初から水平じゃないし、足の動きは全部少しずつ違うけれど、使えないレベルではないのでそのまま。手を切りそうなバリなどは自分で削ったりもした。たぶん買ってそのまま使いたい人を切り捨てるメーカーなんでしょね。

2つ並べてみた。使っているとチタンの焼き色だけはいい感じについてくる。

まずはトライアド君から。鍋なしだと大きく炎が上がるのでビビってしまってピンぼけ。

鍋をのせるとこの通り。実際にはもうちょっと大きいサイズの鍋をのせないと火力などの効率も悪いので縦長なクッカーとは相性は良くない。ちなみに、鍋が冷たいうちは底で水滴ができて、鍋が傾いていることもあってぽたぽた落ちるので室内での使用には向かないはず。後で簡単に掃除出来るようなところで使ったほうがいいかも。せっかく燃焼部が地面から離れているのだからもうちょっとちゃんと作ってくれれば机の上でも使えそうなだけに残念。ちなみに、燃焼部のフタを外してやっても炎の形や勢いはほとんど変化しない。これって見かけだけってこと?

次はデカゴン君。周辺のジェット部に火がつくには思いのほか時間がかかるので点火する時は本体に燃料をかけて火だるま状態から始めてやるとすぐ使える状態になる。真似する場合は火事にならないよう自己責任でどうぞ。

クッカーをのせるとこんなかんじ。このシリーズの3兄弟の中で最も実用に近いのではないだろうか。ゴトクと一体型で、しかも大きな鍋をのせてもそれほど不安定にならずに耐えてくれる。トライアドと比べるとこの安定感は本当に大きな進歩である。作りは相当にアレでも故障する要素は極端に少ないので、外で使う分にもまだ不安は少ない。ミニマムなセットで持って行くのであれば土台部分を切ってもう少し小さくしてみてもいいかもしれない。風防さえ工夫してやればちゃんと使える道具なんじゃないかな
・・・・やっぱり趣味用かも。

VARGO(バーゴ) デカゴンチタンストーブ
なぜか手元に2種類もあるこのキワモノをまたもや引っ張り出してきました。

VARGO(バーゴ) チタントライアドXEストーブ
久しぶりに値段見たけど、こんなものでこれほど高いものをよく買ったものだと我ながら呆れるお値段。より実用的なものはもっと安いんだし。

VARGO(バーゴ) デカゴンチタンストーブ
これもナチュで売っていた。昔は結構レアアイテムだったのに、普及したのね。まあ、こいつは一体型だしちょっと踏んでもたぶん壊れないし、小さめの鍋もなんとか使えるので買うならこっちでしょうね。買ったときは継ぎ目に穴が空いていてアルコール漏れまくりだったので耐火パテで穴を塞いだのはいい思い出。その後穴から漏れることはないのでおおむね満足。穴開き率は結構高いので通販でハズレを引いたら自分で修理したほうが交換より確実かも。トライアドも最初から水平じゃないし、足の動きは全部少しずつ違うけれど、使えないレベルではないのでそのまま。手を切りそうなバリなどは自分で削ったりもした。たぶん買ってそのまま使いたい人を切り捨てるメーカーなんでしょね。

2つ並べてみた。使っているとチタンの焼き色だけはいい感じについてくる。

まずはトライアド君から。鍋なしだと大きく炎が上がるのでビビってしまってピンぼけ。

鍋をのせるとこの通り。実際にはもうちょっと大きいサイズの鍋をのせないと火力などの効率も悪いので縦長なクッカーとは相性は良くない。ちなみに、鍋が冷たいうちは底で水滴ができて、鍋が傾いていることもあってぽたぽた落ちるので室内での使用には向かないはず。後で簡単に掃除出来るようなところで使ったほうがいいかも。せっかく燃焼部が地面から離れているのだからもうちょっとちゃんと作ってくれれば机の上でも使えそうなだけに残念。ちなみに、燃焼部のフタを外してやっても炎の形や勢いはほとんど変化しない。これって見かけだけってこと?

次はデカゴン君。周辺のジェット部に火がつくには思いのほか時間がかかるので点火する時は本体に燃料をかけて火だるま状態から始めてやるとすぐ使える状態になる。真似する場合は火事にならないよう自己責任でどうぞ。

クッカーをのせるとこんなかんじ。このシリーズの3兄弟の中で最も実用に近いのではないだろうか。ゴトクと一体型で、しかも大きな鍋をのせてもそれほど不安定にならずに耐えてくれる。トライアドと比べるとこの安定感は本当に大きな進歩である。作りは相当にアレでも故障する要素は極端に少ないので、外で使う分にもまだ不安は少ない。ミニマムなセットで持って行くのであれば土台部分を切ってもう少し小さくしてみてもいいかもしれない。風防さえ工夫してやればちゃんと使える道具なんじゃないかな
・・・・やっぱり趣味用かも。

VARGO(バーゴ) デカゴンチタンストーブ